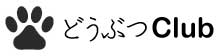今年は「ねずみ年」です。
ネズミは色々な病原体を媒介するため、公衆衛生上も注意しなければならない動物の一つ
です。
代表的なものとして、サルモネラ症やレプトスピラ症、またネズミに寄生するノミやダニに
よるペストやツツガムシ病などもあります。
特にペストは14世紀に大流行し、世界中で8,500万人が死亡したと言われています。
そんな嫌われ者のネズミですが、日本には天然記念物に指定されているネズミがいます。
世界中で沖縄や奄美大島、徳之島だけに生息する、ケナガネズミとトゲネズミです。
ケナガネズミ(下写真)は、頭胴長約25cm、尾長約30cmの大型のネズミで、日本産として
は最大です。
全身褐色で、背中には他の毛よりもはるかに長い7cmほどの毛が生えていることから、この
名前が付きました。
また、尾の先半分が白いのもケナガネズミの特徴で、樹上生活をしながら、木の実や昆虫など
を主食にしています。
トゲネズミ(下写真)は頭胴長約15cm、尾長約10cmで全身黒褐色です。
名前の由来どおり、2cmほどの先のとがった毛(トゲ)で覆われており、木の実や昆虫など
が主食です。
ところでトゲネズミには、他の哺乳類とは異なる特徴があります。
大部分の哺乳類では、オスはXYという性染色体を持っており、Y染色体にある性決定遺伝子
によってオスになると考えられています。
ところが、トゲネズミのオスはY染色体を持っていないにも関わらず、オスになれるのです。